子どものきれいな歯並びには、食事のときの姿勢がとても重要ということは、前回のvol.1でもお伝えしました。
でもそれだけでなく、食事中のクセや舌の使い方などが、歯並びの乱れに影響していることもあります。
前回に引き続き、歯並び育児の専門家・山上あかりさんに、正しい姿勢のために必要な食事環境づくりについて詳しく教えていただきました。
2025.05.07
0才から考える、きれいな歯並びの育て方 vol.2「理想の食事環境と体づくり」
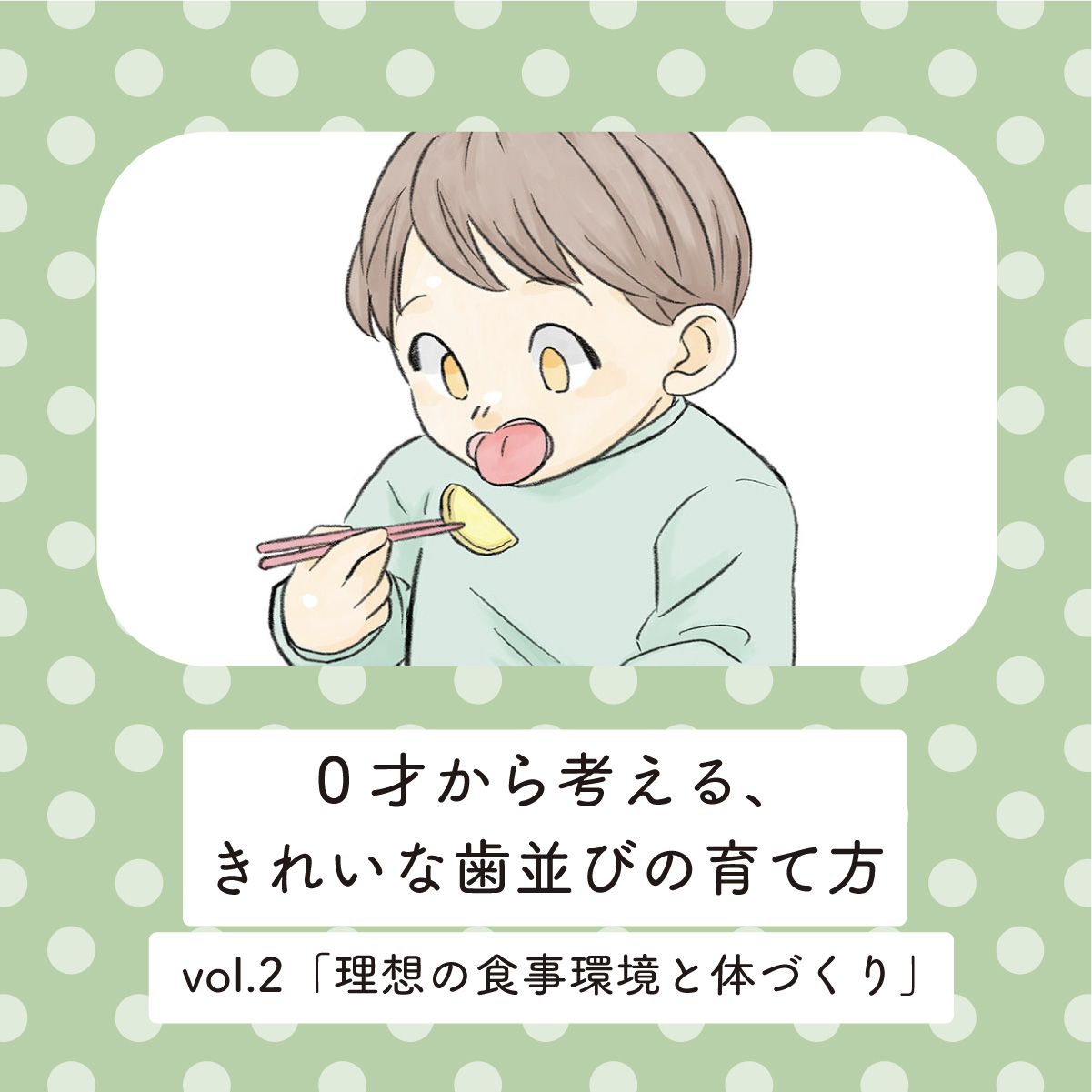
▼これまでの記事

山上あかりさん
《教えてくれた人》
正しい姿勢には環境×体幹がポイント!
ー「もう小学生だから」「下の子に椅子を譲りたいから」などの理由で、大人と同じ椅子に変えても大丈夫ですか?
このご質問、とてもよくいただきます。
私は、ベビーチェアでも年齢が上がってもずっと使えるものをおすすめしています。
近年では、リビングで学習するスタイルが一般的になり、食事用の椅子がそのまま勉強用の椅子になることも増えています。
勉強のときも、食事時と同じように「安定した姿勢」が取れることで、きれいな字が書けたり、集中力が高まったりと、良い効果がたくさんあります。
そのため、大人用の椅子で理想的な座り姿勢がきちんと取れるようになるまでは、ぜひ、yamatoyaさんの「すくすくチェア」のような、足裏がしっかりつく椅子を使い続けてほしいと思います。
ちなみに、すくすくチェアは耐荷重が80キロまであるので、お子さまが成長して使わなくなった後も、ママやパパが引き続き使うこともできるんです。
赤ちゃんのころからずっと使ってきた思い出の椅子を、大人になっても使えるのは嬉しいですよね。

ー椅子などの環境を整えることの大切さは、yamatoyaとしてもずっと大切にしているところです。環境を整える以外にも、正しい姿勢を保つためにできることはありますか。
自然に正しい姿勢をとりやすくなる、環境を整える椅子を準備することは大切です。
でも、姿勢を支えているのは“体の力”、つまり体幹なんです。
環境を整えることは大切ですが、それだけでは不十分で、子どもの身体の発達も同時にサポートしていく必要があります。
たとえば、椅子の高さや足置きなどの調整がしっかりされているのに、「座ってもすぐグラグラしてしまう」「姿勢がすぐに崩れて、食事に集中できない」「立ち上がったり、ウロウロ歩き回ってしまう」といったお悩みがある場合、体幹が育っていないことが原因かもしれません。
体幹を育てていくことで姿勢の安定が保てるようになり、結果的に噛みにくさや飲み込みにくさ、丸飲み、消化不良などの食事に関するお悩みの改善にもつながっていきます。
ーでは、体幹を鍛え、正しい姿勢を育てるには、どうすればいいのでしょうか?
正しい姿勢を育てるためには、日々の発達を見守り、サポートすることがとても大切です。
姿勢を支える筋力やバランス感覚は、赤ちゃんが遊んだり、動いたりする中で少しずつ育まれていきます。
赤ちゃん期であれば、首がすわる、寝返りをする、ズリバイやハイハイをするといった発達のステップを大切にしましょう。
左右の動きに偏りがあったり、「バタフライ型」のズリバイ(足を広げて体を引きずるような動き)をしていないかなども、観察してみてください。
離乳食を始めるタイミングも注意が必要です。
「離乳食を始める時期=ひとりで座れる」ではないことを理解し、腰がまだ安定していない時期には正しい座位のサポートをしてあげましょう。
まだちゃんと座れていないのに、離乳食開始の月齢が近いからと焦って始める必要はありません。
幼児期には、よじ登る、ジャンプする、バランスをとるような遊びをたくさん取り入れることで、姿勢を保つ力が育ちます。
こうした日々の発達を意識しながら、子どもの年齢や成長段階に合わせたサポートをしていくことが、きれいな歯並びを育てるための土台になります。
ーそのほかにも、気をつけた方がいいことはありますか?
体幹をきたえて、正しい姿勢をとれる環境を整えることができても、「どう食べているか?」という部分が整っていなければ、やはり歯並びに影響が出てしまいます。
噛んだり、飲み込んだりする動作は、実は舌やお口のまわりを鍛える筋トレのような役割を果たしています。
たとえば、いつも左右どちらかで食べ物を噛むクセがあったり、「迎え舌」といって舌や下あごを前に突き出して食べ物を迎えにいくようなクセがあると、それだけで毎日の食事の積み重ねによって歯並びが乱れてしまうこともあります。

子どもは、ママや家族が座っている方向、または食べ物が置いてある方向を意識して食事をすることが多く、たとえばママがいつも右側に座っていたり、食べ物が右側に多く並んでいたりすると、自然と体が右を向いて食べるようになります。
それが続くと、姿勢の左右のバランスが崩れたり、いつも同じ側で噛む「噛みグセ」がついてしまい、噛み合わせの問題にもつながりやすくなるのです。
食事中にテレビがついていて、子どもがそちらを向いたまま食べる場合も、同様のリスクがあります。
ですので、ママができるだけ子どもの真正面に座ってあげたり、食事の時間はテレビを消すといったちょっとした環境づくりが、実は歯並びのためにもとても大切なんですよ。
おうちでできる!環境 × 体の発達サポート
ー家庭でできる、正しい姿勢を育てる工夫があれば教えてください。
まずは、先ほどもお話ししたように、子どもが自然と良い姿勢をとれる環境を整えてあげることが大切です。
椅子はその子の成長に合わせて、こまめに高さや奥行きを調整していくことも忘れずに行ってください。
外食やおうち以外での食事の際は、あまり神経質にならなくても大丈夫。
いちばん大切なのは、子どもがいちばんよく食べる場所、つまり、家庭の食卓の環境を整えておくことです。
離乳食や食事の悩みが尽きないという場合には、子どもの性格や集中力、これまでの発達の過程、姿勢を支える体の力など、さまざまな要素が絡んでいることが多いです。
そんなときは、まずはおうちでできることから始めてみましょう。広い場所で思いきり体を動かしたり、裸足で過ごす時間を増やしたり、ハイハイや歩く動きをたくさん取り入れてみてください。
「もうハイハイは終わっちゃったし、今さら…」と思う方もいるかもしれませんが、心配はいりません。
幼児期でもハイハイ遊びはとても有効です。トンネルくぐりなどを使って、どんどん体を動かしていきましょう。
そして最後に、ぜひ習慣にしてほしいのが「いただきます」のひとこと。
日本では食べる前に「いただきます」、外国でも食前に手を合わせたりお祈りをしたりしますよね。実はこれ、体の前で手を合わせることで、姿勢をまっすぐ安定させる効果もあるんです。命への感謝とともに、姿勢を整えるきっかけとしても、毎日の食事の中に取り入れてみてくださいね。
***
きれいな歯並びの土台は、食事中の姿勢や舌の使い方といった日々の積み重ねの中にあります。
そして、その姿勢を支える体の力は、遊びや生活の中で少しずつ育まれていくもの。椅子を見直すこと、家庭の環境を整えること、そして子どもの体の発達をあたたかく見守ることから、始めてみましょう。
次回、vol.3では、離乳食の始まるタイミングで、気をつけたいことについてお聞きしていきます。
SHARE
こちらもおすすめ
わたしたちは、子ども家具メーカー「yamatoya」です。
家具メーカーとして
親子の成長を応援したい。
子ども家具をつくってきた歴史は、
子育て情報蓄積の歴史でもあります。
リアルな体験や役立つお話を
全国の子育て世代のみなさんと
共有したいと思っています。
▼商品について詳しく知りたい、商品が見られるお店を知りたい
▼商品を購入したい、ショップのお得な情報を知りたい














